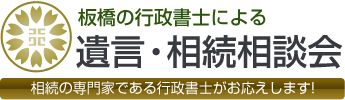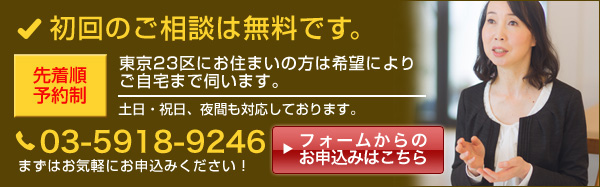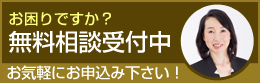トップページ > ペットに遺産を遺す方法
ペットに遺産を遺す方法
ペットに遺産を遺す方法
今やペットは家族の一員です。一般社団法人ペットフード協会の調べによると、ペットを飼育している世代は50歳代が最も多く、次に60歳代となっています。
犬や猫の寿命も人間同様に延びてきています。
「自分にもしものことがあったら、この子たちはどうなるのだろう」と考えたとき、
必要になるのは、まずは世話をしてくれる人。
そして、ペットが天寿を全うするまでの飼育費。
※ペットは法律では「モノ」として扱われるので、遺言書で直接、ペットに遺産を遺すことはできません。
では、どうしたら良いでしょう。
ペットの面倒をみてくれる人を探して、世話をしてくれることを条件に財産を譲るという方法を取ることが出来ます。
①負担付遺贈
②負担付死因贈与
③ペット信託
負担付遺贈とは
遺言によって、財産を贈与することを「遺贈」と言いますが、「遺贈」を受ける人(受遺者)に一定の義務(負担)を負わせることです。
遺言は一方的な意思表示なので、相手の同意は必要ありません。
<注意する点>
贈与する人の同意は必要ないとはいえ、ペットの世話と言う義務を課すことになります。ペットを飼うことを拒否したい場合には、遺贈を放棄されてしまう可能性があります。事前に相手とよく話し合って承諾を得ておくことが重要です。
◆受遺者の責任の範囲は、遺贈される目的物の価格を超えない限度とされています。遺贈する金額は、ペットの平均余命や、毎月掛かっているペットフード代、病院代などや、何かあった時のために予備的資金を計算し、十分な世話をしてもらえるように考慮しなければなりません。
◆遺言者である飼い主が亡くなった後、ペットがきちんと世話をされているかどうかをチェックする、遺言執行者を指定しておくことが大切です。
万一、受遺者がペットの世話をしないなど遺言の内容を守らない場合に、相当な期間を定めて、改善を請求することが出来、それでも改善されない場合には、遺贈の取り消しを家庭裁判所に申立てることができます。
◆他の相続人の遺留分を侵害しないよう配慮した内容にすることが大切です。
※負担付遺贈は後日の争いを防ぐためにも、公正証書遺言で作成しましょう。
負担付死因贈与とは
死因贈与とは、贈与をする人の死亡によって効力が発生するという内容の契約を結んでおくことです。
通常の贈与は「今、あげます」という契約ですが、死因贈与は「私が死んだら財産あげます」ということです。
負担付死因贈与とは死亡を原因とした贈与契約に、ペットの世話と言う義務(負担)を付けたものです。
遺贈と大きく違う点は、遺贈は一方の意思だけでも出来ますが、契約は双方の同意が必要という点です。契約の相手方は個人ではなく、法人でも受遺者になることが出来ます。
●飼い主が元気なうちに、相手と契約を交わします。
契約は、当事者の合意だけでも成立しますが、後日のトラブルを防ぐために書面を作成しておきましょう。
●受贈者から放棄される心配がありません。
双方の合意による契約なので、受贈者は原則、放棄することはsできません。
●負担付死因贈与も「執行者」を指定しておくことが出来ます。
死亡が効力発生の原因となる死因贈与は、性質上、「遺贈」に類似するものとして「遺贈」の規定が準用されるので、執行者を指定することができます。
執行者は負担付遺贈と同様、きちんと世話がさせていない場合に改善するよう請求することが出来、場合によっては死因贈与の撤回を家庭裁判所へ申し立てることができます。
ペット信託とは
飼い主が元気なうちに、あらかじめペットの世話をしてくれる人と飼育費を用意しておき、飼い主が認知症や重病等でペットを育てられなくなったときに、新しい飼い主にペットを託し、財産管理者から新しい飼い主へ飼育費を渡してもらうという制度です。
飼い主(委託者)と財産管理者(受託者)の間で信託契約を結ぶことにより成立します。飼育費は金融機関に開設した受託者名義の信託口の口座で管理し、そこから新しい飼い主さんへ飼育費が支払われることになります。
<特徴>
●飼い主の死亡だけではなく、病気や認知症の場合など、様々な状況に対応できます。
●信託した飼育費は、飼い主の他の財産とは分別し管理されますので、ペットのための財産を守ることができます。
万一、飼い主が認知症等で後見人が付いたとしても、信託された飼育費には後見人の権限は及びません。
●飼育費が正しく管理されているかどうか、ペットが適正に飼育されているかをチェックする「信託監督人」を置くことが出来ます。
●新しい飼い主の方にも万一のことがあった場合に、更にその次の飼い主も決めておくことができます。
※ペット信託は、飼い主に何かあった場合にペットを守るための仕組みです。相続人である家族の理解が大前提となりますので、遺言書と併用して、他の相続人へ配慮することにより、ペットがより安心して暮らせるようになります。
愛玩動物飼養管理士で動物法務士である行政書士がペットの暮らしを守る対策についてのご相談に対応いたします。